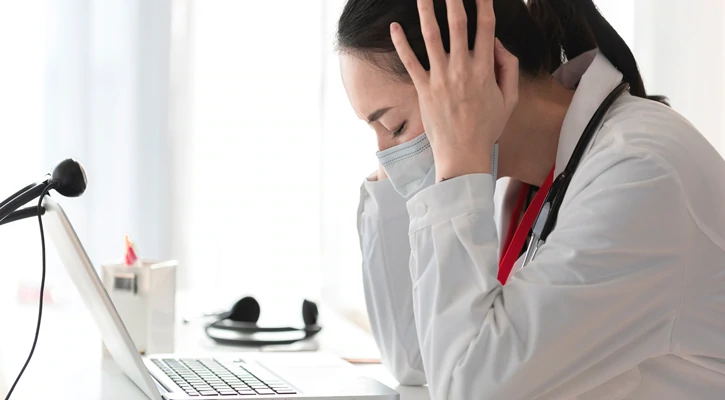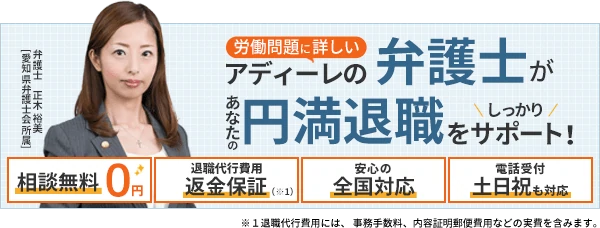パワハラ・セクハラはもうイヤ!有利に退職したい勤務医の退職手続とは?
公開日:
更新日:
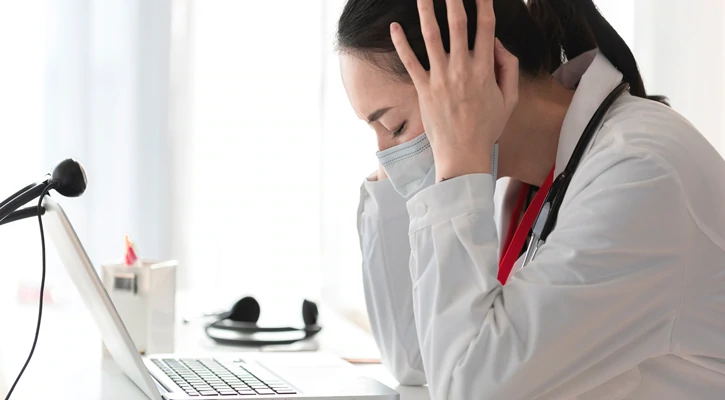
勤務医のなかには、職場でのパワハラやセクハラに苦しめられながら、それでも我慢して仕事を続けている方も多いと思います。夢や希望を持って実現した医師という職業を全うしたいなら、パワハラやセクハラが横行する病院からは一刻も早く退職するべきです。同時に、パワハラやセクハラをした上司等のみならず、病院に対しても、その法的責任を追及することを検討されてはいかがでしょうか。
このコラムでは、パワハラやセクハラ、病院を退職することについてご説明したうえで、退職手続の代行を弁護士に依頼することで受けられるメリットについてもお伝えします。
- 今回の記事でわかること
-
-
パワハラ・セクハラに対する損害賠償請求
-
退職手続を進めるにあたり知っておくべきポイント
-
弁護士に退職代行を依頼するメリット
- 目次
-
-
勤務医とパワハラ・セクハラ
-
パワハラ・セクハラとは?
-
パワハラ・セクハラに対する損害賠償請求について
-
今後パワハラ・セクハラを受けないための対策とは
-
勤務医が退職手続の際に知っておくべきポイント2つ
-
1.退職時の有休消化について
-
2.退職を妨げる不当な拘束への対応について
-
弁護士に退職手続の代行を依頼するメリット
-
まとめ
勤務医とパワハラ・セクハラ
勤務医のなかには、上司等からのパワーハラスメント(以下、「パワハラ」といいます)およびセクシャルハラスメント(以下、「セクハラ」といいます)による精神的苦痛を受けながら、対処方法を見つけることができずに病院での勤務を続けている方がいらっしゃいます。
日本医療労働組合連合会青年協議会の「医療・介護・福祉職場ではたらく青年職員に対するハラスメントに対する調査」結果報告(2018年5月)によると、3人に1人がパワハラやセクハラなどのハラスメントを受けたことがあると回答し、その半数が退職までも考えているとのことです。
以下では、パワハラやセクハラの定義、パワハラやセクハラを受けた場合にいかなる請求ができるのかなどについてご説明いたします。
パワハラ・セクハラとは?
パワハラとは、職場における優越的な関係を背景とした言動であり、業務上必要かつ相当な範囲を超えたもので、それにより労働者の就労環境を害するものをいいます。
具体的には、部下の医師を叩くといった暴行はもちろんのこと、「馬鹿だ」のように口汚く罵ることや、「どの病院でも使えない」などのように人格を否定することが、これに当たります。また、業務上の必要がないにもかかわらず、1人でこなせない過大な人数の患者を担当させる、その医師の能力から判断して通常は担当することのない検査業務だけを行わせる、外科医なのに手術をさせない、といったこともこれに当たります。
次に、セクハラについてご説明します。セクハラとは、相手方の意に反する性的言動のことをいい、これに対する労働者の対応により不利益を受ける対価型と、労働者の職場環境が害される環境型に分類されます。
対価型の具体例としては、たとえば、性的な事柄についての質問や、肉体関係を持つことの強要を拒否した医師について、降格させる、仕事を与えない、などといったことが挙げられます。
また、環境型の具体例としては、特定の医師について不倫をしていることを職場に触れ回る、女医の腰や胸などを頻繁に触るといったことを行い、職場で仕事を続ける意欲を低下させるといったことが挙げられます。
上記でご紹介したパワハラやセクハラは、身体、名誉感情、人格権などを侵害するものであり、違法と評価されます。
パワハラ・セクハラに対する損害賠償請求について
勤務医は、病院に雇用されている労働者です。実際にパワハラやセクハラを受けた場合、パワハラやセクハラをした上司等に対し、不法行為に基づく損害賠償請求(民法第709条)をすることができるのはもちろん、上司等の使用者たる病院に対しても、使用者責任に基づく損害賠償請求(民法第715条)をすることが可能です。
金銭的賠償を受けることで、パワハラやセクハラによって被った精神的苦痛が慰謝されるということになります。
今後パワハラ・セクハラを受けないための対策とは
また、今後も同様のハラスメントを受けないようにする方法として、病院にパワハラやセクハラを受けていることを相談し、必要な措置を採ってもらうのも一案です。
労働施策総合推進法第30条の2は、事業主に、労働者に対するパワハラを防止する措置を採ることを義務づけており、パワハラを受けたと相談してきた労働者について解雇やそのほかの不利益な取扱いをしてはならないとしています。
そして、男女雇用機会均等法第11条、同法第11条の3および育児・介護休業法第25条は、事業主に、労働者に対するセクハラを防止する措置を採ることを義務づけており、セクハラを受けたと相談してきた労働者について、解雇やそのほかの不利益な取扱いをしてはならないとしています。
これらの法律に基づき、病院にパワハラやセクハラを受けたことを相談することで、事実確認後、上司等のハラスメントの行為者に対する是正措置が採られるとともに、再発防止のための措置が採られ、以後、ハラスメントを受けなくなる可能性があります。
なお、労働施策総合推進法第30条の2は、中小事業主については、2022年4月1日から施行されます。
-
※病院の場合は、出資金の総額が5,000万円以下か、常時使用する労働者の数が100人以下のいずれかに該当すると、中小事業主とされます。
勤務医が退職手続の際に知っておくべきポイント2つ
これまでの解説で、パワハラ・セクハラに対して対処方法があるということはおわかりになったと思います。とはいっても、勤務医のなかには、損害賠償請求をするにしても、病院に在職したままでは仕事がやりにくくなるのではないか、病院から有形・無形の不利益を受けるのではないか、との不安を抱く方も多いでしょう。
また、病院に相談したとしても、そもそもパワハラやセクハラが横行している病院であれば、再発防止の措置をとるなどの誠実な対応を期待することは難しいかもしれません。
上記のような場合には、ひとまず退職し、落ち着いたところで、損害賠償請求を行うという方法もあります。
ここでは、勤務医が退職手続を進める際に、知っておくべき2つのポイントについて解説いたします。
1.退職時の有休消化について
「パワハラ・セクハラに対する損害賠償請求について」で申し上げたとおり、勤務医は病院に雇用されている労働者であり、期間の定めなく雇用されている方が多いと思います。期間の定めなく雇用されている場合、病院に退職の意思表示をしてから2週間経過すると、雇用関係が終了するとされています(民法第627条1項)。
そのため、期間の定めなく雇用されている勤務医は、退職届を病院に提出後、2週間が経過すれば退職できます。
なお、退職届を提出してから2週間は雇用関係が存続しているため、その間は出勤する必要があります。しかし、年次有給休暇(労働基準法第39条)が残っていれば、これを消化することが可能です。したがって、残存する年次有給休暇の日数によっては、退職届を提出してから一度も出勤することなく病院を退職することもできるのです。
2.退職を妨げる不当な拘束への対応について
勤務医が退職を決意し、退職届を提出しても、病院が退職を認めないとしてくることがあります。医師を十分に確保できていない病院の場合、勤務医に退職されてしまうと困るからです。
しかしながら、病院が退職届を提出したにもかかわらず、退職を認めないとすることは、民法第627条1項に正面から反し、勤務医を不当に拘束するものとして許されません。
また、病院によっては、「退職するには3ヵ月以上前に退職届を提出すること」というような規定を設けているところもあります。そして、病院が勤務医に対し、この規定を根拠として、3ヵ月間は出勤するよう求め、その間に退職届を撤回させようとすることも考えられます。
しかしながら、民法第627条1項の2週間を超えて、退職までにその意思表示から3ヵ月以上を要求することは、労働者を不当に雇用契約に拘束するものであり、そうした病院の規定は無効とされます(高野メリヤス事件・東京地判昭和51年10月29日参照)。
ですから、退職届の提出から3ヵ月後でないと退職できないというような規定が置かれていても、勤務医が退職届を提出してから2週間経過後に退職することは可能なのです。
弁護士に退職手続の代行を依頼するメリット
勤務医が退職手続の際に知っておくべきポイント2つをご紹介しましたが、これらを知っているからといって、スムーズに退職できるとは限りません。病院から退職を認めないなどと言われ、引き留められた場合、勤務医ご自身で民法の規定を挙げて適宜反論することは難しいといえますし、病院とのやり取りを続けることの精神的負荷も大きいでしょう。
そこで、退職手続の代行を弁護士に依頼し、代理人たる弁護士を通じて、病院に退職の意思表示をし、あわせて年次有給休暇取得の請求もし、弁護士が病院とやり取りすることで、退職手続を進めることをおすすめします。
弁護士でない業者に退職代行を依頼しても、病院から何らかの反論がなされたとき、その業者は、弁護士法第72条により、反論に理由がないとして交渉することは許されません(いわゆる非弁行為に該当します)。
弁護士であれば、病院からの反論にも適宜対応できますし、病院も真摯に対応する可能性が高いといえます。さらにパワハラやセクハラの損害賠償請求について相談し、有効な法的助言も得られるかもしれません。
まとめ
パワハラやセクハラを受けてお困りの勤務医の方におすすめしたいのは、大きな精神的負荷を抱えた状態で病院の勤務を続けるよりも、退職して精神的負荷のない状態で損害賠償請求をするのかを検討したり、ご自分のスキルや希望の働き方に合った新しい職場を探したりすることです。
退職に関するやり取りを病院と行うことに不安を感じ、躊躇されている方もいらっしゃるでしょう。そのような場合には、退職手続の代行を弁護士に依頼し、病院とのやり取りを任せることをおすすめします。
退職したいと思っていてもどうすればいいかわからない勤務医の方は、ぜひ一度アディーレにご相談ください。
監修者情報
-
資格
-
弁護士
-
所属
-
東京弁護士会
-
出身大学
-
中央大学法学部
弁護士に相談に来られる方々の事案は千差万別であり、相談を受けた弁護士には事案に応じた適格な法的助言が求められます。しかしながら、単なる法的助言の提供に終始してはいけません。依頼者の方と共に事案に向き合い、できるだけ依頼者の方の利益となる解決ができないかと真撃に取り組む姿勢がなければ、弁護士は依頼者の方から信頼を得られません。私は、そうした姿勢をもってご相談を受けた事案に取り組み、皆様方のお役に立てられますよう努力する所存であります。